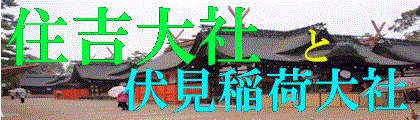 |
住 所 京都市伏見区深草藪之内町 |
御鎮座千八百年を平成二十三年に迎える大阪住吉大社と
1300年にわたって、人々の信仰を集める京都伏見稲荷大社の参拝記録です。
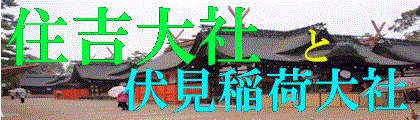 |
住 所 京都市伏見区深草藪之内町 |
説明文は基本的には「住吉大社セミナー」に参加したとき配布されたの「住吉っさん」を参考にさせていただきました。
|
住吉大社の前を紀州街道が |
また近くには「熊野街道」も
| 熊野街道 熊野街道は、和歌山県熊野本宮への参詣道で、平安時代から鎌倉時代にかけて「蟻の熊野詣」といわれる程、多くの人々の往来で賑わった街道です。 京都から淀川を舟で下り、八軒家(中央区天満橋京町)に上陸した人々は上町台地を縦断、途中所在する「熊野九十九王子」(住吉区では津守王子)と呼ぶ遥拝所をたどりながら熊野三山に至りました。 |
| 熊野街道は住吉大社の東側を 住吉区内では万代池西側や住吉大社東側・墨江丘中学校東側、遠里小野小学校西側付近などに旧街道の面影を残しており、その顕彰碑も建てられています。 |
住吉大社は1800年の歴史が
| 大和朝廷の頃住吉津(すみのえのつ)があった所 住吉大社は古代大和王権の外交・航海に関連した神社で、遣隋使、遣唐使の守護神で、津守氏は遣唐神主として遣唐使船に乗船したと言われています。 遣隋使、遣唐使は、大社南部の細江川(通称・細井川。古代の住吉の細江)にあった仁徳天皇が開いたとされる住吉津(「墨江ノ津」「住之江津」すみのえのつ)から出発し大陸へと出発したそうです。 住吉津は、上代( 奈良時代・平安時代 初期)は、シルクロードにつながる主な国際港でもあったと言われています。 |
では境内へ
 |
| 阪堺電軌の通っている道路を横断し、大きな石碑の向こうに鳥居が見え、その奥に反橋がある。 |
境内へ入ると反橋があります(雨の日は滑りますのでご注意!)
|
反 橋 |
| 東に進むと住吉の象徴として有名な通称太鼓橋といわれている「反橋(そりばし)」に着きます。 |
|
鎌倉時代に創建された太鼓橋 |
住吉鳥居の柱は丸柱でなく方形(四角柱)です
|
住吉鳥居 |
 |
| この鳥居は「住吉鳥居」とよばれているもので、柱の断面が通常の鳥居のような円形でなく、方形であり珍しい形です。 |
|
住吉大社 |
鳥居をくぐると、直ぐ「楼門」があり、広場を隔てて楼門の東側に「第三本宮」が建てられています。
|
楼 門 |
|
門はいくつもあります |
|
拝殿と本宮(本殿) |
| 第三本宮(本殿)の奥に第二本宮、その奥に第一本宮 第四本宮は第三本宮の右隣にあります。 第一本宮から第四本宮の(四つの本宮それぞれに拝殿が付けられているが、拝殿も本宮と同様、全て西側が正面となっており、造りは四つの拝殿全て同じです。 この拝殿の正面から本宮に向かって遙拝します。 |
 |
 |
|
本殿四棟はいずれも国宝に指定されています、 |
|
これらの建造物は全て国宝に指定されています |
|
|
|
|
境内の全て
|
住吉神宮寺跡碑 |
|
住吉文庫 |
| 第一本宮の北側に土蔵様の二階建ての建物が「住吉文庫」であります。 住吉文庫は1723年(享保8年)に大阪、京都、江戸の書店が勝運発展を願って建立し、寄進した書籍を納めていたといいます。 この住吉文庫は大阪最古の図書館としてよく知られています。 |
|
どこの門だったか忘れました。 |
|
飛鳥時代から寺社建築の「金剛組」 |
|
|
摂社・末社 |
|
住吉大社には数多くの摂社・末社がある。 |
|
石舞台・南門 |
 |
| 五所御前の南側に「石舞台」があります。 この「石舞台」は日本三大舞台の一つといわれており、1596〜1615年(慶長年間)に豊臣秀頼の寄進によるものとされ、重要文化財に指定されています。 |
|
五所御前 |
 |
| 第一本宮の南側に石の玉垣に囲まれ、内に杉の木が植えられている「五所御前」と呼ばれている場所があります。 かつて、神功皇后が住吉大神を祀る地を決めるとき、この杉の木に鷺が三羽とまったのを見て、大神がこの地を望んでいると考えここに大神を祀ることに決めたと伝えられている場所で、「高天原(たかまがはら)」とも呼ばれているといわれています。 |
|
校倉風の蔵? |
夫婦楠 |
| 境内には数多くの燈籠が寄付されている写真のものは「呉服古着業」とありました。 | |
|
吉祥殿 |
|
吉祥殿は休憩も出来ますが結婚式なども行われます |
|
豪華ホテルのようなロビーでした |
|
|
吉祥殿の2階から境内が良く見えます。 |
次は大阪住吉から京都の伏見稲荷へ
|
伏見稲荷 |
伏見稲荷大社は京都市伏見区にある神社で、稲荷神を祀る全国約4万社の稲荷神社の総本宮です。
稲荷山の麓に本殿があり、稲荷山全体を神域とします。
|
参拝者駐車場から大社の方へ進みます。 |
途中京阪電車の線路を渡り参道商店街へ |
参道商店街の鳥居を潜ると「楼門」へ出ます。
|
秀吉が母大政所の病悩平癒祈願のため造営 |
|
バスの発車までに「奥の院まで行こうと張り切ったので |